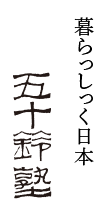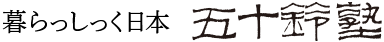茶の湯つれづれ噺 ~お茶とお菓子とともに~
- 内容:
- 受講者の方々にお点前をしていただき、経験のない方々には、茶筅を振ってお茶を点てていただき、五十鈴茶屋製の季節のお菓子をお楽しみいただきます。
今回のシリーズは、点前所作の意味に関すること、茶の湯の釜に焦点を絞って、それぞれの相違点について、皆さんと共に考えたいと思います。是非受講してください。きっと、新しい発見があります。
(講師の都合により日時が変更になる場合がございます)
---------
4月17日(木)「点前の成立」 ~点前の成立と台子発案の諸説~
茶の点前順序は、いつごろから行われるようになったのか。「茶の湯古事談」では『南浦紹明が入宋して、帰朝する際径山寺より飾り用仏具棚(茶の湯棚)を持ち帰り、博多の崇福寺に伝えた。その後天竜寺の夢窓国師がそれを使用して茶を点てた』とあります。また南方録には『台子の点前で天皇に献茶した』とあります。点前は何時頃から行われるようになったのか、考えましょう。
---------
5月15日(木)「点前とは」~「利休道歌」と「南方録」の点前とは~
「利休道歌」には「点前には弱み捨ててただ強く、されど風俗いやしきを去れ」など謙虚でおごらない態度の点前と云っています。また「南方録」では『茶の湯は仏の教えを体して修業を続け、悟りを開くことにある』と述べられています。点前をするということは、どういうことなのか、どういう心構えで点前の稽古をすればよいのか、考えてみましょう。
---------
6月19日(木)「点前発生のいろいろ」
炉は四隅を落としています。元々炉の四隅は落としていなかった。何時頃から炉の四隅を落とすようになったのか、また、誰が考え出したのか。点前が終わり、建水を持って帰るとき、お客様に尻を向けてもよいと教えています。しかし、もともとは前向きに帰っていたのです。何時頃から建水周りをするようになったのか、考えてみましょう。
---------
7月17日(木)「点前所作の意味」
点前所作には、それぞれ意味があります。「座った時、手を組むのは」「扇子を前に礼をするのは」「茶筅通しの意味は」「鏡柄杓の意味は」等々それぞれに意味があります。更に濃茶点前で「お服かげんはいかがですか」と挨拶するのは。また、炉の点前で中仕舞をするのは…皆さんとともに考えてみましょう。お点前のお稽古が更に楽しくなります。
---------
8月21日(木)「茶の湯の釜」について① 釜の種類 ~芦屋釜・天明釜・京釜~
芦屋釜の原料は夏井ヶ浜の砂鉄で、銅の成分が多く含まれています。天明釜は栃木県佐野市の山から採取した砂鉄で炭素が多く含まれています。京釜は、全国から砂鉄の材料を集めて、芦屋の材料と天明の材料の中間的な材質の砂鉄を作りました。そして、紹鴎や利休など、茶人の好みによって作られたので地紋や形が多種多様なものになりました。江戸時代になると西村、大西、名越の名家が栄え、金沢では宮崎寒稚が活躍しました。それぞれの釜の特徴を考えてみましょう。
---------
9月18日(木)「茶の湯の釜」について② 釜の扱い方 ~保存と手入れ~
釜は茶道具の中でも扱い方の難しいもののひとつです。その中でも釜の仕舞方には注意が必要です。高価な釜であってもしまい方が悪ければ耐久性に影響します。釜は茶の湯の道具として長い時代使われ続け、時代がついていく楽しみがあります。釜に「時代がつく」というのは、時、使い方、金属の酸化、錆、傷、埃、手入れ等の要因が関わってきます。その要因を理解することが「時代をつける」秘訣です。良い釜に良い時代をつけるには、どうすればよいのか考えましょう。
- 日時:
- 2025/04/17(木)・05/15(木)・06/19(木)・07/17(木)・08/21(木)・09/18(木) 18:30~20:00
- 講師:
- 淺沼 宗博
- 定員:
- 20名
- 料金:
- 全6回分 会員 10500円 ビジター 13500円 (6回分、茶菓代・材料費含む)
- 場所:
- 五十鈴塾左王舎
講座は終了しました