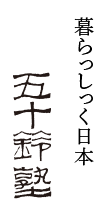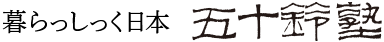茶の湯つれづれ噺 ~お茶とお菓子とともに~
- 内容:
- 受講者の方々にお点前をしていただき、経験のない方々には、茶筅を振ってお茶を点てていただきます。
また、五十鈴茶屋製「季節のお菓子」を毎回、茶菓子としてお楽しみいただけます。
さて、今回のシリーズは、前回のシリーズで変更になった釜の種類と扱い方、および炉開きから名残の茶までの茶の湯の一年、茶人の逸話の数々等を詳解します。日常生活に活かされることが沢山あります
興味のある方、是非受講してください。きっと、新しい発見があります。
(講師の都合により日時が変更になる場合がございます)
---------
10月16日(木)「茶の湯の一年」 ~口切の茶から名残の茶まで~
初夏に摘んで茶壺に寝かされていた新芽を11月初旬に初めて使います。これを口切といいます。
この時、茶人たちは炉を開きます。茶人の正月です。
炉開きの時期や由来、名残の茶等について考えてみましょう。
---------
11月20日(木)「茶の湯の釜」 ① 釜の種類~芦屋釜・天明釜・京釜~
芦屋釜の原料は夏井ヶ浜の砂鉄で鋼の成分が多く含まれています。天明釜は栃木県佐野市の山から採取した砂鉄で炭素が多く含まれています。京釜は、全国から砂鉄の材料を集めて、芦屋と天明の材料の中間的な材料の砂鉄を作りました。そして茶人の好みによって作られたので地紋や形が多種多様なものになりました。それぞれの釜の特徴を考えましょう。
---------
12月18日(木)「茶の湯の釜」 ② 釜の扱い方~保存と手入れ~
釜は茶道具の中でも扱い方の難しいもののひとつです。その中でも釜の仕舞い方には注意が必要です。高価な釜であっても、仕舞い方が悪ければ耐久性にも影響します。釜に「時代が付く」というのは、使い方、錆、手入れ、保存他、いろいろな要因が関わってきます。その要因を理解することが「時代をつける」秘訣です。釜の扱い方について考えましょう。
---------
1月15日(木)「濃茶と薄茶」~濃茶と薄茶の区別はいつごろからか~
松屋会記天文5年(1536)正月6日の会に「炉ニツリ物 タジニスンギリ茶盌水指大合子天目夕陽ニテ御茶点て…」とあり、茶盌と夕陽天目の二つの茶盌が書かれています。この頃には濃茶と薄茶の区別がなされていたのではないかと思われます。
濃茶が先か薄茶が先か、共に考えてみましょう。
---------
2月19日(木)「茶人の逸話」 ①宗旦流の点前
宗旦流の点前は、茶盌にお湯を入れるとき、一滴畳に落とすのが定石であった。近衛家の侍医であった山科ノ道安が「塊記」の中で述べています。
宗旦流の点前とは、どのようなものであったのか、考えてみましょう。
---------
3月19日(木)「茶人の逸話」 ② 利休の教え
唐物茶入れの蓋は無傷の物が当時は慣例でありました。
現在では、巣の入っている茶入れの蓋も使われています。
どのような経緯で使われるようになったのか紹介します。
また、現在立礼席で使われている朱塗りの大傘は、誰が最初に使ったのか、逸話から紹介します。
- 日時:
- 2025/10/16(木)・11/20(木)・12/18(木)・2026/01/15(木)・02/19(木)・03/19(木) 18:30~20:00
- 講師:
- 淺沼 宗博
- 定員:
- 20名
- 料金:
- 全6回分 会員 10500円 ビジター 13500円 (6回分、茶菓代・材料費含む)
- 場所:
- 五十鈴塾左王舎
講座予約は終了しました