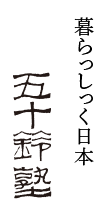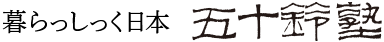神崎塾長のつぶやき
令和7年春号「白酒」
白酒が、三月三日の雛まつりの供えものとなって久しいことは、周知のとおりです。でも、白酒は、そのために造られたわけではありません。春先のこの時によく造られたことから、混同が生じたのです。
江戸での白酒の元祖は、鎌倉町(現在の千代田区内神田)の豊島屋と伝わります。慶長年間(一五九六~一六一五年)の開業といいますから、江戸開幕早々のことです。
ちなみに、この場合の白酒は、精白した糯米を味醂に浸しておき、それを臼で挽き、さらに清酒を加えて造った微発酵酒で、合成酒の一種です。その配合によっては、以て非なる酒にもなります。たとえば、粘り気が強いと練酒となりますが、北九州あたりではそれが好まれた、といわれます。
酒度は薄く、甘みが強い。そのため、江戸での白酒は、当初は下戸の酒として卑しまれもしました。また、子供用の酒ともされました。
ところが、この時期にかぎってよく売れだしたのです。たぶん、清酒の配合も多くなったのでしょう。
狂歌にもあります。
君はただかまくら河岸のしろ酒か
もうきれたとはつれなかりける
白酒は、ひとつには清酒の代用として飲まれました。当時、江戸に出まわっていた酒は、灘からの下り酒でした。樽廻船で運ばれてきます。ところが、正月(旧正月)を過ぎたころから春にかけての海は時化るので、市中に出まわる酒が途切れがちでした。そのために、白酒の需要が増しもしたのです。
江戸の風俗事典といわれる『守貞謾稿』(喜田川守貞著、嘉永六=一八五三年)には、「春を専らとす。又、此買の荷ふ所、必ず山川を唱す」とあります。ここでいう「山川」は、それより先に京都六条の酒屋で造っていた白酒の呼称です。京の雅風にあこがれ、それにあやかる傾向が江戸には潜在してありました。ということから、豊島屋でも「山川」を冠して売りました。そこで、「山川」は、江戸でも白酒の代名詞にもなったのです。
また、豊島屋の白酒が売られる時期は、ちょうど雛まつりの時期でもありました。そのため、雛まつりに白酒が供わるようにもなったのです。
という歴史からみると、三月三日は女子の節供だからやさしい白酒を供える、などという理屈は通らないでしょう。俗説にもいつわりあり、といえそうです。
過去のつぶやき
伊勢 美し国から
番組概要
「伊勢美し国から」は、日本人古来の生活文化を「美し国」伊勢より発信する15分番組です。
二十四節気に基づいた神宮の祭事や三重に伝わる歴史、文化、人物、観光、民間行事などを紹介。古の時代から今に伝わる衣食住の知恵と最新のお伊勢参り情報を伝えます。
五十鈴塾は、日本文化の再発見を目指して各種講座及び体験講座などを開催してきた実績を活かして、この「伊勢美し国」番組企画を行っています。