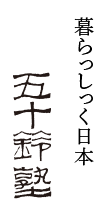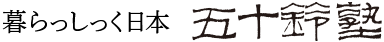神崎塾長のつぶやき
令和7年秋号「秋なす」
ナスは、もっとも季節感あふれる野菜のひとつ、といえるでしょう。
六月から九月にかけて多く出回りますが、とくにおいしいとされるのが秋なすです。「秋なすは嫁に喰わすな」という諺は広く知られるところです。
これは、一般的には、嫁いびりの姑根性をあらわす言葉とされてきました。つまり、いちばんおいしい秋なすを嫁に食べさせるのはもったいない、という解釈が広まっています。「末の初もの」といわれるように、季節の終いにできる野菜は初物と同じく味がよい、として古くから珍重されており、ナスもその例外ではありません。それを嫁に横取りされてなるものか、というわけです。
ただ、そのほかにもいくつかの説があります。
ひとつは、嫁の身を案じるという善根説。たとえば、中国の本草学の基本書とされる『本草綱目』(一五九六年)で、すでにそのことにふれているので、古くから広く知識が共有されていたとしてよいでしょう。『開本草』(刊行年不詳)には、「茄子は性冷にして腸胃を冷やす。秋に至りて毒最も甚し」とあります。秋ナスは体を冷やすから毒だと、姑が自分の経験から冷え性の嫁を気遣って多食を戒めた、という説が流布するのも当然です。
ほかに、秋なすは種子が小さいので、子種が貧弱だったり少なくなるのを嫌ってのこと、という縁起かつぎの説もあります。私見にすぎませんが、このあたりの俗説が妥当なのかもしれません。
さらに、ここでの嫁は「嫁が君」、つまりネズミのことであるとし、美味な秋なすをネズミにひかれてはたいへんだ、という解釈の異説もあります。
これほど異説珍説が派生する野菜もないでしょう。それほどに親しみやすい野菜ということなのでしょうか。あの紫黒色の艶やかな輝きが日本人の色彩感に合ったのでしょうか。いずれにせよ、秋なすは美味なもの。一方で、食べ過ぎれば体を冷やす恐れがあることも事実でしょう。
さて、秋なすをどのように調理して味わいましょうか。私は、ウルカ(鮎のはらわたの塩漬け)と合わせて炒める――これが酒の肴としておつなものなのです。
過去のつぶやき
伊勢 美し国から
番組概要
「伊勢美し国から」は、日本人古来の生活文化を「美し国」伊勢より発信する15分番組です。
二十四節気に基づいた神宮の祭事や三重に伝わる歴史、文化、人物、観光、民間行事などを紹介。古の時代から今に伝わる衣食住の知恵と最新のお伊勢参り情報を伝えます。
五十鈴塾は、日本文化の再発見を目指して各種講座及び体験講座などを開催してきた実績を活かして、この「伊勢美し国」番組企画を行っています。