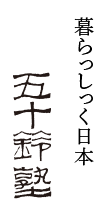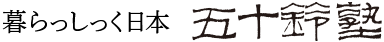神崎塾長のつぶやき
令和7年冬号「霜月あれこれ」
「霜月」という表記が、カレンダーの一一月のページにあります。
現在のカレンダーではそうするしかありませんが、霜月は、陰暦(旧暦)での数え方です。したがって、実際には約一ヵ月ずれて、新暦での一二月のころの気象となります。
また、陰暦の一0月、一一月、一二月を「霜枯れ三月」ともいいました。ところによって違いますが、そのころは太陽の光が弱くなり、空気も冷え冷えとしてきます。暁方には、霜が降ります。
霜が降ったら、農作は進みません。作物が、まさに霜枯れるのです。それゆえに、収穫作業はそれまでにすませなくてはなりませんでした。
秋まつり、とはいいますが、そう簡単には日が定まりません。平場では稲の収穫を終えればそれでよいのですが、山村では畑作物の始末もしなくてはなりません。稲の収穫がすべてではないのです。
それを、「霜くる前にもう一働き」といいました。したがって、それを終えての「霜月まつり」となるのです。
鳥居や社殿の脇に幟が立ちます。それは、ただの目印ではありません。古くは、山頂がさまざまな神霊や精霊が集くところでした。それを、柱を立て幟を掛けて招くのです。その幟柱の先端に杉の葉を束ねてとりつけるのが、その象徴として伝わります。
そこに夜っぴいての神楽もでてきます。たとえば、備後や備中での荒神式年神楽(荒神神楽)。例年氏神に奉納する宮神楽よりも、長時間かけて古きをたどります。これを「霜月神楽」ともいいました。宮崎での高千穂・銀鏡・米良神楽なども霜月神楽です。
とくに山村では、秋の夜長ならぬ霜月の夜長なのです。
神楽が終わりに近づいたころには、あたり一面に霜が降りています。寒くもあります。白々と夜が明けてきます。ゆっくりとゆっくりと明けてきます。そこに朝日が差しこみます。そして、霜が晴れてきます。これも、ゆっくりとゆっくりと。神楽見物の帰り道、草むらの霜がかすかに凍って白く輝いてみえたものです。
そういえば、「霜月の薬喰い」という言葉もありました。
収穫を終えた後ですから、食べものが豊富です。農作物にかぎりません。干し柿はまだ渋いですが、かんころ芋(干し芋)は、火にあぶれば食べられます。みかんも出はじめます。新米を醸したにごり酒もあります。食餌は、薬餌です。腹がもたれたら、「霜月粥」もよろしいでしょう。この時期なら、白い粥も遠慮せずに食べられます。
正月はあれどもやがて冬ごもり……。霜月は、遠くの春の待ちはじめでもあるのです。
過去のつぶやき
伊勢 美し国から
番組概要
「伊勢美し国から」は、日本人古来の生活文化を「美し国」伊勢より発信する15分番組です。
二十四節気に基づいた神宮の祭事や三重に伝わる歴史、文化、人物、観光、民間行事などを紹介。古の時代から今に伝わる衣食住の知恵と最新のお伊勢参り情報を伝えます。
五十鈴塾は、日本文化の再発見を目指して各種講座及び体験講座などを開催してきた実績を活かして、この「伊勢美し国」番組企画を行っています。